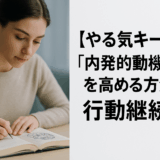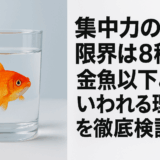勉強中に音楽(BGM)を流すタイプでしょうか?
「音楽を聴きたいけれど我慢している」「無音のほうが集中できる気がする」と感じる人も多いでしょう。
今回は、「勉強中に音楽を流しても良いのか?」「どんな音楽が適しているのか?」について、メリット・注意点・おすすめのジャンルを解説します。
上手に音楽を取り入れれば、受験や定期テスト、資格試験の勉強効率が格段にアップする可能性があります。
メリット①:スピードアップ
音楽には「行動誘導効果」があり、テンポや音量が私たちの行動に影響を与えます。たとえば、テンポが速い音楽を聴くと自然と動作も早くなるのです。
ある実験では、スーパーで流す音楽のテンポによって来店者の滞在時間が変化しました。ゆったりしたテンポ(BPM:72)では平均127.53秒、速いテンポ(BPM:94)では108.93秒と、明確な差が見られました。
「勉強したくない…」とダラダラしてしまう時は、テンポの速いBGMを流してみましょう。音楽に背中を押されて、自然と勉強モードに切り替えやすくなります。
メリット②:集中力アップ

スタンフォード大学の研究によると、音楽は「学習能力」や「認知能力」を高める効果があると報告されています。
メロディやリズムの変化に注意を向けることで、周囲への集中力が鍛えられるというのです。また、音情報として取り込んだ内容は、後から思い出しやすくなる傾向があります。
視覚・触覚に加え、聴覚も使って学習すると記憶の定着率が高まります。勉強に音楽を取り入れることで、集中力と記憶力の両面に効果が期待できます。
メリット③:リラックス効果
リラックスできる音楽には「感情誘導効果」があります。病院や歯科医院で穏やかな音楽が流れるのもこの効果を利用したものです。
副交感神経が優位になることで不安や緊張が緩和され、落ち着いた気持ちで勉強に取り組めます。
「集中したいけど力が入ってしまう」そんな時は、お気に入りのリラックス音楽で心を整えるのが効果的です。
メリット④:マスキング効果

音楽には「マスキング効果」もあります。つまり、周囲の雑音を自然にかき消してくれるのです。
図書館・カフェ・自宅など、どこで勉強していても小さな生活音が気になりますよね。時計の音、人の話し声、車の通過音などに気を取られやすい人には音楽が助けになります。
適切な音楽を流せば、こうした雑音を自然にかき消して集中力が持続しやすくなります。
音楽を流す際の注意点
一方で、好きな曲や歌詞がある音楽は注意が必要です。
J-POPや洋楽、テンポの速すぎる曲は、つい口ずさんでしまったり、感情が動きすぎて集中が途切れやすくなります。
歌詞のある音楽は言葉の処理に脳のリソースを使ってしまうため、学習内容に集中できなくなることも。
単語の暗記や問題演習など、頭を使う学習には向いていないので注意しましょう。
勉強に集中できるおすすめ音楽

勉強中におすすめなのは「歌詞のない音楽」です。以下のジャンルは特に集中力を高めやすいとされています。
- ジャズ
- クラシック
- ボサノバ
- ピアノインストゥルメンタル
- ヒーリングミュージック
また、雨音や風の音、焚き火や小川のせせらぎなどの環境音も人気です。
「リラックス効果」や「集中持続」を目的とした音楽を選ぶのがポイントです。
YouTubeなどで「勉強用BGM」「作業用BGM」と検索すれば、すぐに試聴できる音楽がたくさん見つかります。
あらかじめ“勉強用BGM”を決めておけば、音楽がスイッチのような役割を果たして集中しやすくなります。
まとめ
適切なBGMを取り入れることで、勉強効率は驚くほど変わります。
- スピードアップ:行動のテンポが上がる
- 集中力アップ:記憶力・認知力の向上
- リラックス効果:緊張をほぐし気持ちを整える
- マスキング効果:周囲の雑音を自然にカバー
歌詞付きやお気に入りすぎる曲は集中を妨げる恐れがあるので、選曲には注意が必要です。
ジャズ・クラシック・ヒーリング系など、テンポが穏やかで歌詞のない音楽を選び、音楽の力を上手に活用しましょう。
音楽を味方につけて、快適な勉強時間を手に入れてください。